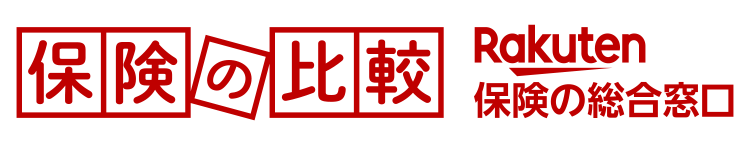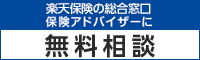生命保険の役割
生命保険の役割
死亡保障の必要額はこう考えよう
最終更新日:2022年11月25日
<死亡保障の必要額は2つの軸で考える>
万が一の後の必要額を見積もるには、「いくら」を「いつまで」という2つの軸で考えます。例えば、生活費として毎月20万円(「いくら」)を20年間(「いつまで」)といった具合に、必要額と必要期間を整理すると、その時点での必要額の総額が計算できます。教育費は今後必要になる小学校、中学校、高校、大学などの就学期間ごとに、それぞれ公立か私立かを選んで計算した金額を合計します。住居費は万が一のことがあった後、遺族がどこに住むかによって異なる金額を生涯に渡って見積もることになります。
<万が一の後の「収支」を考える>
万が一のことがあった後の必要額のうち、自分たちではカバーしきれない分を生命保険で補うことになります。逆に言えば、十分なお金と収入があるなら生命保険は必要がないとも言えます。
そのカバーしきれない分、すなわち「不足分」がどれくらいあるのか?を知るために、万が一のことがあった後の必要額から、遺族が見込める収入および現在の貯蓄などを差し引いて計算します。見込める収入の中心となるのは、遺族年金や配偶者の老後の年金です。また、配偶者に勤労収入や家賃収入がある人もいるでしょう。これら見込める“収入”と今後必ず訪れるライフイベントにかかる支出を見積もり、差し引き不足する分を生命保険で準備するというわけです。
死亡保障の必要額 = 万が一の後の支出 - 万が一の後の収入(貯蓄含む)
- 生命保険で準備する死亡保障の必要額は?(例)
-
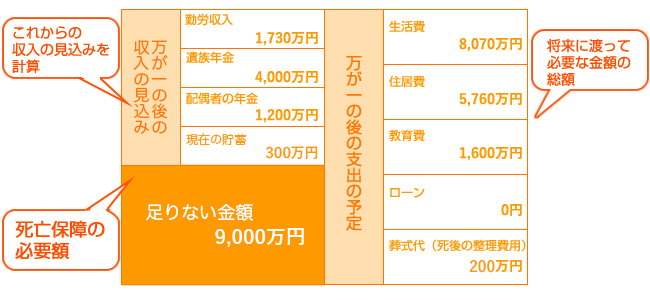
※その他見込める準備済みの金額:会社からの死亡退職金・預貯金
※事例で示した金額はあくまでも1つの例にすぎません。個別の状況により、生命保険で準備する死亡保障の必要額は異なります。
<必要な保障は年々変化する>
死亡保障の必要額を計算しても、その金額は毎年変化します。一年経てば、単純に一年分の生活費や教育費が減るからです。よって死亡保障の必要額は、下記のように年々減少します。ただし、子どもが増えたりするなど必要となる資金が増えると必要額は増加します。また、万が一のことがあった後に遺族が実現したいライフイベントや購入したいものが新たに増えた場合も必要額は増加します。死亡保障の必要額をグラフで表すと概ね右肩下がりの下図のようになります。これが、生命保険の死亡保険金額や保険期間を決める際の参考イメージとなります。
- 死亡保障の必要額の変化のイメージ
-
就学前の子が一人、マイホーム取得済みの30代会社員の例
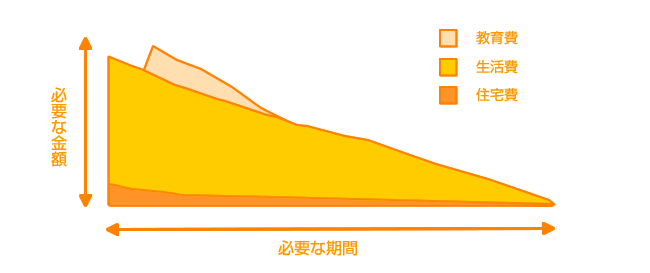
※事例はあくまでも1つの例にすぎません。個別の状況により死亡保障の必要額は異なります。
2211761(4)-2311
- 同じカテゴリのページ
- 関連ページ