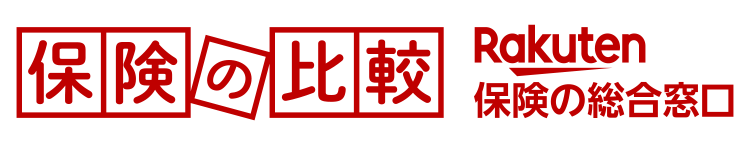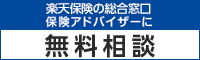人によって違う必要な保障額と保障期間の考え方
人によって違う必要な保障額と保障期間の考え方
遺族年金を知っておこう
最終更新日:2022年11月24日
<どの遺族年金が受給できるか知っておこう>
公的年金制度には「国民年金」、「厚生年金」があり、遺族年金もそれぞれから支給されますが、亡くなった人の公的年金の加入状況や「18歳到達年度の末日を経過していない子」がいるかどうかで、受給できる遺族年金の種類と額は異なります。
- 出典:
- 日本年金機構「遺族年金ガイド 令和4年度版」
(https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/kyufu.files/LK03-3.pdf)
-
亡くなった人 国民年金に加入
(国民年金第1号被保険者、第3号被保険者)厚生年金に加入
(同2号被保険者)受給できる
遺族年金の種類遺族基礎年金 遺族基礎年金
遺族厚生年金
※公務員が加入していた年金制度である「共済組合」は、2015(平成27)年10月1日から「厚生年金に一元化」され、公務員も厚生年金に加入することとなりました。そのため、一元化後に亡くなった場合は、遺族厚生年金が支給されます。ただし、一元化前の共済加入期間等の部分については、遺族共済年金として受給することになります。 (出典:国家公務員共済組合連合会ホームページ「年金を受給されている方向けQ&A」(https://www.kkr.or.jp/nenkin/q_and_a/)・文部科学省共済組合「被用者年金一元化パンフ」(https://www.monkakyosai.or.jp/kouhou/pdf/hiyoushanenkin_ichigenka.pdf))
遺族基礎年金
亡くなった国民年金の被保険者や老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある人等に生計を維持されていた、子のいる配偶者または子が受給できます。
子とは「18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子」または「20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子」をさします。 (出典:日本年金機構ホームページ「遺族基礎年金(受給要件・対象者・年金額)」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html))
【遺族基礎年金額】
遺族基礎年金額は次のとおりです(※2022(令和4)年度額)。
年金額=777,800円+子の加算
子の加算:第1子、第2子 各223,800円
第3子以降 各74,600円
【受給額の例】
配偶者および18歳到達年度の末日を経過していない子が3人の場合: 1,300,000円
配偶者および18歳到達年度の末日を経過していない子が2人の場合: 1,225,400円
配偶者および18歳到達年度の末日を経過していない子が1人の場合: 1,001,600円
遺族厚生年金
会社員や公務員等の厚生年金に加入中の人、老齢厚生年金の受給資格期間が25年以上ある人等が亡くなった場合に、以下の優先順位にしたがって受給できます。なお、亡くなった人に生計を維持されていたことが要件です。
- 妻(※)
- 子(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)
- 死亡当時に55歳以上の夫
- 死亡当時に55歳以上の父母
- 孫(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の子)
- 死亡当時に55歳以上の祖父母
※夫が亡くなったときに30歳未満の子のない妻の受給権は5年を経過すると消滅します。
(出典:日本年金機構ホームページ「遺族基礎年金 受給要件・対象者・年金額 遺族厚生年金の受給対象者」(https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/izokunenkin/jukyu-yoken/20150401-04.html))
【遺族厚生年金額】
遺族厚生年金額は平均標準報酬額等により異なり、次のように計算します。
(平均標準報酬月額×7.125/1000×2003(平成15)年3月までの被保険者期間の月数+平均標準報酬額×5.481/1000×2003(平成15)年4 月以降の被保険者期間の月数)×3/4
※ただし、被保険者期間が300月未満の場合には、300月とみなして計算
【中高齢寡婦(かふ)加算】
遺族厚生年金では、遺族厚生年金を受給する妻に「中高齢寡婦加算額」(583,400円(※2022(令和4)年度額)が加算される場合があります。加算されるのは40歳から65歳になるまでの間で、以下のいずれかに該当する場合です。
- 夫が亡くなったとき40歳以上65歳未満であり、生計を同じくしている「子がいない妻」
- 遺族厚生年金と遺族基礎年金を受けていた「子のある妻(※)」が、子が18歳到達年度の末日に達した(障害の状態にある場合は20歳に達した)ため、遺族基礎年金を受給できなくなったとき
※40歳に達した当時、子がいるため遺族基礎年金を受けていた妻に限る
<会社員が死亡した場合の遺族年金の受給例>
厚生年金に加入しており、妻と18歳到達年度の末日を経過していない子どもがいる会社員の夫が死亡した場合、妻は遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給することができます。子どもや妻の年齢によって、受給できる金額は変化していきます。
例: 夫死亡時 妻35歳、第1子 3歳、第2子 1歳
夫の厚生年金被保険者期間 2012(平成24)年4月より120ヶ月間
平均標準報酬額 30万円
妻の老齢基礎年金は満額とする
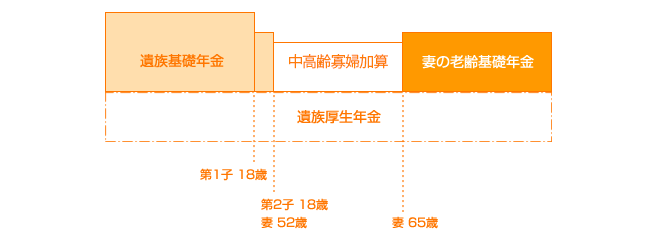
<受給できる年金額の推移の例>
| 第1子が18歳 になるまで |
第2子が18歳 になるまで |
妻が65歳 になるまで |
妻65歳以降 | |
|---|---|---|---|---|
| 遺族厚生年金 | 約37万円 | 約37万円 | 約37万円 | 約37万円 |
| 遺族基礎年金 | 約123万円 | 約100万円 | − | − |
| 中高齢寡婦加算 | — | — | 約58万円 | − |
| 妻の老齢基礎年金 | — | − | − | 約78万円 |
| 年金額合計 | 約160万円 | 約137万円 | 約95万円 | 約115万円 |
※年金額はいずれも年額で「万円未満四捨五入」、2022(令和4)年度額
※65歳以上の配偶者が受け取る遺族厚生年金は、自身の老齢厚生年金の金額により金額が調整されますが、ここでは考慮していません。
社会保険制度の取り扱いは2022年10月1日現在の制度に基づくもので、全ての情報を網羅するものではありません。将来的に制度が変更となる場合がありますのでご注意ください。なお、個別の取扱いについては所轄の年金事務所もしくは社会保険労務士などにご確認のうえ、ご自身の責任においてご判断ください。
2211700(9)-2311
- 同じカテゴリのページ