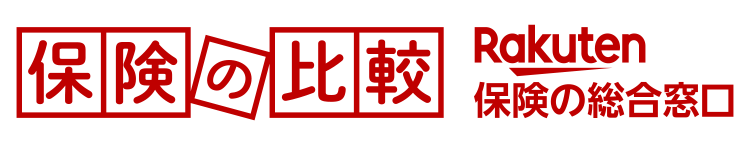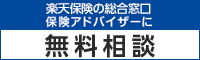人によって違う必要な保障額と保障期間の考え方
人によって違う必要な保障額と保障期間の考え方
若い夫婦
最終更新日:2022年11月21日
<若い夫婦世帯の死亡保障の考え方>
子どものいない若い夫婦世帯が考えておきたいのが、残された配偶者の生活費についてです。子どもがいない場合、配偶者に万が一の事があったときの公的な遺族保障額が少ないため、生活費を何らかの収入でカバーする必要があります。
収入を得る手段は、正社員として働き続ける、パートで働く、実家に戻り両親の世話になるなど人によって異なりますが、いずれもこれらの収入で不足するならば、その部分を生命保険で準備しておくのもひとつです。
例えば、現在共働きで、生活費については特に心配ないというケースでは、葬儀費用などの死後の整理費用を中心に準備することになります。専業主婦(夫)で配偶者に万が一のことがあった場合、その後は働くつもりというケースなら、配偶者が職に就くまでの期間に必要な生活費の準備が必要になるかもしれません。
<若い夫婦世帯の死亡保障の必要額と期間はこう考える>
若い夫婦世帯の死亡保障の必要額は、残された配偶者が得ると見込まれる収入によって変わります。すぐに働けるのであれば、生命保険で準備すべき生活費は少なくなりますし、働くまで時間がかかりそうな場合や働くことができない場合は、生命保険で準備する生活費は大きくなります。
また、加入している年金制度が国民年金か厚生年金かで、受給できる遺族年金の金額も異なるため、万が一の場合にどのくらいの遺族年金を受取ることができるかも知っておきましょう。なお、遺族厚生年金を受給できる場合でも、子どものいない30歳未満の妻の受給は5年間のみとなっているため注意が必要です。
※遺族年金の詳細は「遺族年金を知っておこう」をご覧ください
- 例1.共働き(二人とも正社員)の場合
-
必要性 期間 考え方 金額 葬儀費用 ○ 一生涯 統計データなどから算出 200万円 生活費 × - - - 必要額の合計 200万円
共働きの場合、万が一の事があっても配偶者自身の収入があるため、生活費は自身の収入で補うことができるでしょう。
- 例2.会社員の妻(夫)で無職の場合
-
必要性 期間 考え方 金額 葬儀費用 ○ 一生涯 統計データなどから算出 200万円 生活費 ○ 就業までの期間 遺族年金の不足分 500万円 必要額の合計 700万円
生活費の必要額は、貯蓄や受給できる遺族年金額によって異なります。国民年金第1号被保険者である自営業者の場合、子どものいない配偶者には遺族年金が支給されないため、保障額を多く準備する必要があります。
2211731(3)-2311