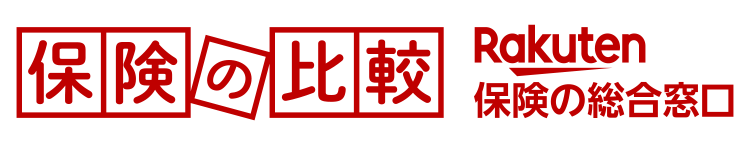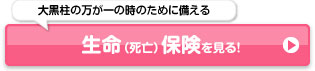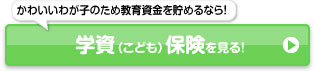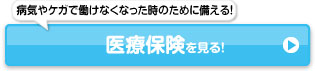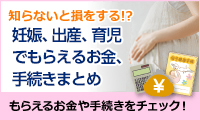知らないと損をする!?
妊娠、出産、育児で
もらえるお金、手続きまとめ
国の少子化対策もあり、妊娠が判明してから出産・育児で休業している期間に、子どもが生まれたことで受けられる給付は年々充実しています。
ここでは、出産・育児に関する「お金と手続き」についてご紹介します。
最終更新日:2022年11月21日
妊婦健診の助成
妊娠が判明すると、妊婦や赤ちゃんの健康状態を確認するため定期的に妊婦健診を受けることになりますが、公費によって妊婦検診の補助を受けられる制度があります。
お住まいの市区町村の窓口に妊娠の届出を行うと、母子健康手帳とともに妊婦健診の受診券が交付されます。何回まで無料で受けられるのか等詳細については、お住まいの市区町村の窓口に確認しましょう。
- 出典:
- 厚生労働省 妊娠がわかったら
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174121.pdf) - 厚生労働省 妊婦健診Q&A
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/boshi-hoken13/dl/02.pdf)
手続き詳しくは市区町村の窓口へ。
児童手当
子どもを育てる家庭の生活の安定や子どもの健やかな成長を支援するため、3歳未満は一律15,000円/月、3歳~小学校修了は第2子までが10,000円/月、第3子以降は15,000円/月、中学生は一律10,000円/月が支給されます(所得制限があります)。
- 出典:
- 内閣府 児童手当Q&A
(https://www8.cao.go.jp/shoushi/jidouteate/ippan.html)
手続き公務員の方は勤務先へ、それ以外の方は市区町村の窓口へ。
出産育児一時金
妊娠や出産は病気ではないため、健康保険などの公的医療保険による診療(療養の給付)を受けることができません。代わりに出産育児一時金として公的医療保険から、原則として1人あたり42万円(※)が支給されます。健康保険組合などでは、独自に出産育児一時金に一定の金額を上乗せして支給(付加給付)している場合もあるため、勤務先の総務や人事担当者などに確認するとよいでしょう。なお、出産育児一時金は夫の扶養に入っている場合も受け取れます。その場合は夫の事業主を通して確認することになります。
※ 2022(令和4)年8月現在
手続き事業主を通して、健康保険の保険者(全国健康保険協会や健康保険組合等)へ申請。
※国民健康保険の被保険者は、市区町村の窓口へ
出産手当金
産前産後の休業期間(産前42日(多胎妊娠の場合は98日)、産後56日)中に、給料の支払いを受けられないときの経済的な支援として、1日につき賃金の3分の2相当額が健康保険から支給されます。健康保険組合などでは、独自に出産手当金に所定の金額を上乗せして支給(付加給付)している場合もあります。
なお、国民健康保険の被保険者や健康保険の被保険者である夫の扶養に入っている場合は出産手当金は受け取れません。
- 出典:
- 厚生労働省 出産したとき(出産育児一時金)
(https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000174135.pdf)
手続き事業主を通して、健康保険の保険者(全国健康保険協会や健康保険組合等)へ申請。
産前産後休業や育児休業期間中の社会保険料免除
会社などで社会保険に加入している人は、産前産後休業や育児休業期間中の健康保険や厚生年金保険の保険料が免除されます。また、国民年金の第1号被保険者(20歳から60歳までの自営業者やその家族・学生・無職の人など)である人は、産前産後期間(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間)の国民年金保険料が免除されます。
- 出典:
- 日本年金機構 従業員(健康保険・厚生年金保険の被保険者)が産前産後休業を取得したときの手続き
(https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/menjo/sankyu-menjo/20140509-02.html) - 日本年金機構 国民年金保険料の産前産後期間の免除制度
(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20180810.html)
手続き会社の社会保険に加入している人は、事業主を通して年金事務所(または健康保険組合)へ、国民年金に加入している人は市区町村の窓口へ申請。
育児休業給付金
女性は産前産後休業期間の終了した日の翌日、男性は出産予定日または出産日から、子どもが1歳(※1)まで支給されます。なお、認可保育所に入れないなど特別な事情がある場合は最長2歳まで支給が延長されます。
支給額(※2)は、育児休業を開始してから180日までは賃金の67%相当額、181日目からは50%相当額です。育児休業給付金は雇用保険から支給されます。
※1父母ともに育児休業を取得する「パパママ育休プラス制度」を利用する場合は1歳2か月まで
※2 育児休業給付金には、1か月あたりの支給額に上限があります
- 出典:
- 厚生労働省 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内 令和4年4月1日から3段階で施行
(https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000789715.pdf) - 厚生労働省 Ⅱ-2産後パパ育休制度(出生時育児休業制度) Ⅱ-2-1産後パパ育休の対象となる労働者
(https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000907662.pdf) - 厚生労働省 育児休業給付の内容と支給申請手続
(https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000986158.pdf)
手続き事業主を通して、公共職業安定所(ハローワーク)へ申請。
児童扶養手当
父母の離婚や、父または母の死亡によるひとり親世帯、父または母が障害の状態にあるなどの世帯に、子どもが18歳に達した以後の最初の3月31日まで支給されます。児童扶養手当には所得制限があり、所得が限度額を超える場合は手当の全部または一部が支給停止になります。
- 出典:
- 厚生労働省 児童扶養手当について
(https://www.mhlw.go.jp/bunya/kodomo/osirase/100526-1.html) - 厚生労働省 児童扶養手当
(https://www.mhlw.go.jp/content/000690051.pdf) - 世田谷区 児童関連手当一覧
(https://www.city.setagaya.lg.jp/mokuji/kodomo/008/002/d00009029.html)
→詳しくは市区町村の窓口へ。
乳幼児等の医療費助成
子どもの保険診療や入院時の食事の自己負担分などが、助成により無料になる制度があります。対象となる年齢や所得制限の有無については、各自治体により異なります。
- 出典:
- 厚生労働省 令和2年度「乳幼児等に係る医療費の援助についての調査」について (https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_20913.html)
- 厚生労働省 乳幼児等医療費に対する援助の実施状況 (https://www.mhlw.go.jp/content/11925000/000827911.pdf)
→詳しくは市区町村の窓口へ。
| 給付の種類 | 給付概要 | 手続き・確認先(原則) | 在職要件 |
|---|---|---|---|
| 妊婦健診の助成 | 妊婦健診の費用が無料 | 市区町村 | - |
| 児童手当 | 3歳未満 1.5万円/月 3歳~小学生※ 1万円/月 ~中学生 1万円/月 ※第3子以降は1.5万円/月 | 市区町村 (出生届提出時) | - |
| 出産育児一時金 | 42万円(1児あたり) | 事業主を通して、 健康保険の保険者 国民健康保険の被保険者は市区町村 | - |
| 出産手当金 | 賃金の2/3相当額 (産前産後休業中) | 事業主を通して、健康保険の保険者 | あり |
| 産前産後または育児休業中の保険料免除 | 健康保険や厚生年金、国民年金※等の保険料が免除 ※産前産後期間のみ | 事業主を通して、年金事務所 国民年金第1号被保険者は市区町村 | あり |
| 育児休業給付金 | 180日まで賃金の67%相当額 181日から賃金の50%相当額(育児休業期間中) | 事業主を通して、 ハローワークへ | あり |
| 児童扶養手当 | ひとり親世帯、父または母が障害者である世帯の子※ ※18歳到達後最初の3月31日までの子 |
市区町村 | - |
| 乳幼児等の医療費助成 | 自治体により一定年齢まで無料 | 市区町村 | - |
出産手当金や育児休業給付金、産前産後休業や育児休業中の保険料免除は退職した場合は受けられません。
※令和4年8月1日現在の法律に基づき、記載しています。
2211739(1)-2311