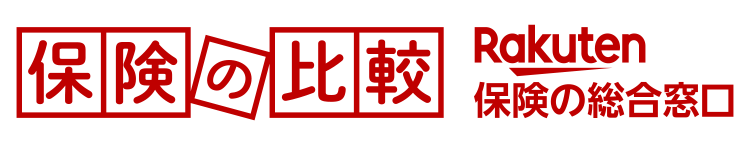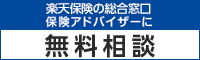人によって違う必要な保障額と保障期間の考え方
人によって違う必要な保障額と保障期間の考え方
子どもが小さい世帯
最終更新日:2022年12月7日
<子どもが小さい世帯の死亡保障の考え方>
子どもが小さい世帯の保障でまず考えなくてはならないことは、万一のことがあったとき、残された家族のその後の長い生活に支障がないお金を残すことです。子どもが社会に出るまでの期間はまだ長く、いろいろな人生の選択肢が考えられます。そして、それらの選択肢によっても民間保険で準備すべき額は変わってきます。そこで、次のようなポイントを参考に、必要となる金額を考えてみましょう。
- 住宅について
配偶者に万一のことがあった場合、その後の住まいをどうするのかを考えてみましょう。今のまま住み続けたい、実家に戻りたい、マイホームを購入したいなどの選択肢があるでしょう。
- 子どもの教育費について
公立中心でよい、私立に通わせたい、留学させたい、などの教育方針の方向性を考えてみましょう。
- 配偶者の働き方について
配偶者に万一のことがあった場合、残された配偶者はそのまま働き続けることができるのか、転職しなくてはならないのか、働けないのかなどによって得られる収入が違ってきます。また、働いていることにより子どもをどこかに預ける必要がありそうなら、その費用も見積もる必要があります。
- その後の生活費について
基本的な生活費が1ヶ月あたりでどのくらいかかるのか、概算で良いので計算してみましょう。現在の家計を参考にするとよいでしょう。
それぞれ必要となる期間が異なりますから、項目別に保障期間と保障金額を考えると検討しやすくなります。
<子どもが小さい世帯の死亡保障の必要額と期間はこう考える>
前述のように、配偶者に万一のことがあった後の生活は多種多様です。どんな人生を送りたいかによって、死亡保障の必要額や期間は大きく変わります。例を見てみましょう。
- 例1. 家族は配偶者と子ども一人。将来はマイホームを購入予定
-
配偶者35歳、子ども一人(幼稚園年長)、進学は中学までは公立、高校は私立、大学は私立文系(自宅)の場合
必要性 期間 考え方 金額 葬儀費用 ○ 万一のことがあったとき 200万円 生活費 ○ 配偶者が老齢年金を受取る年齢まで 不足する生活費×年数 3,600万円 住居費 ○ 住宅取得時 住宅購入費 2,500万円 教育費 ○ 大学までの教育費 統計データから算出 1,040万円 必要額の合計 7,340万円 ※上記の必要額はあくまでも一例であり、実際にかかる金額は個々人の生活環境等により異なります。
この例では、万一の場合の生活費の保障は、残された配偶者が働いて収入を得ても、なお不足する額としています。
また、万一のことがあっても家族が安心して生活できる場所としてマイホームを購入したいという場合には、保険金で購入できるように準備しておくのもひとつです。配偶者の収入だけでもマイホーム購入が可能な家庭であれば、頭金程度を保障額としても良いでしょう。
- 例2. 家族は配偶者と子ども一人。万が一の場合は実家で暮らし、教育費も最小限で良い
-
配偶者30歳、子ども一人(幼稚園年長)、進学は高校までは公立、大学の進学資金は奨学金で補う場合
必要性 期間 考え方 金額 葬儀費用 ○ 万一のことがあったとき 200万円 生活費 ○ 配偶者が老齢年金を受取る年齢まで 不足する生活費×年数 4,200万円 住居費 × - 実家住まいのため住居費不要 - 教育費 △ 高校までの教育費
(大学は奨学金利用)統計データから計算 480万円 必要額の合計 4,880万円
例1に比べると、住居費、教育費の負担が少なくなり、必要な保障額もその分少なくなります。ただし、配偶者が若いため、生活費が必要な期間は長くなるので、生活費分の保障額は大きくなります。
※教育費の参考となる統計データは「万が一の後の支出(教育費)」を参照
※上記の必要額はあくまでも一例であり、実際にかかる金額は個々人の生活環境等により異なります。
<必要保障額を決定するには>
こうして必要となる額を把握した後、考慮しておきたいのは、公的保険制度により残された家族が受け取る遺族年金などの“入ってくるお金”です。“必要となる額”から“入ってくるお金”を差し引いた額が、民間保険で保障を確保すべき「必要保障額」となります。
※遺族年金の詳細は「遺族年金を知っておこう」をご覧ください
2211720(4)-2311
- 同じカテゴリのページ